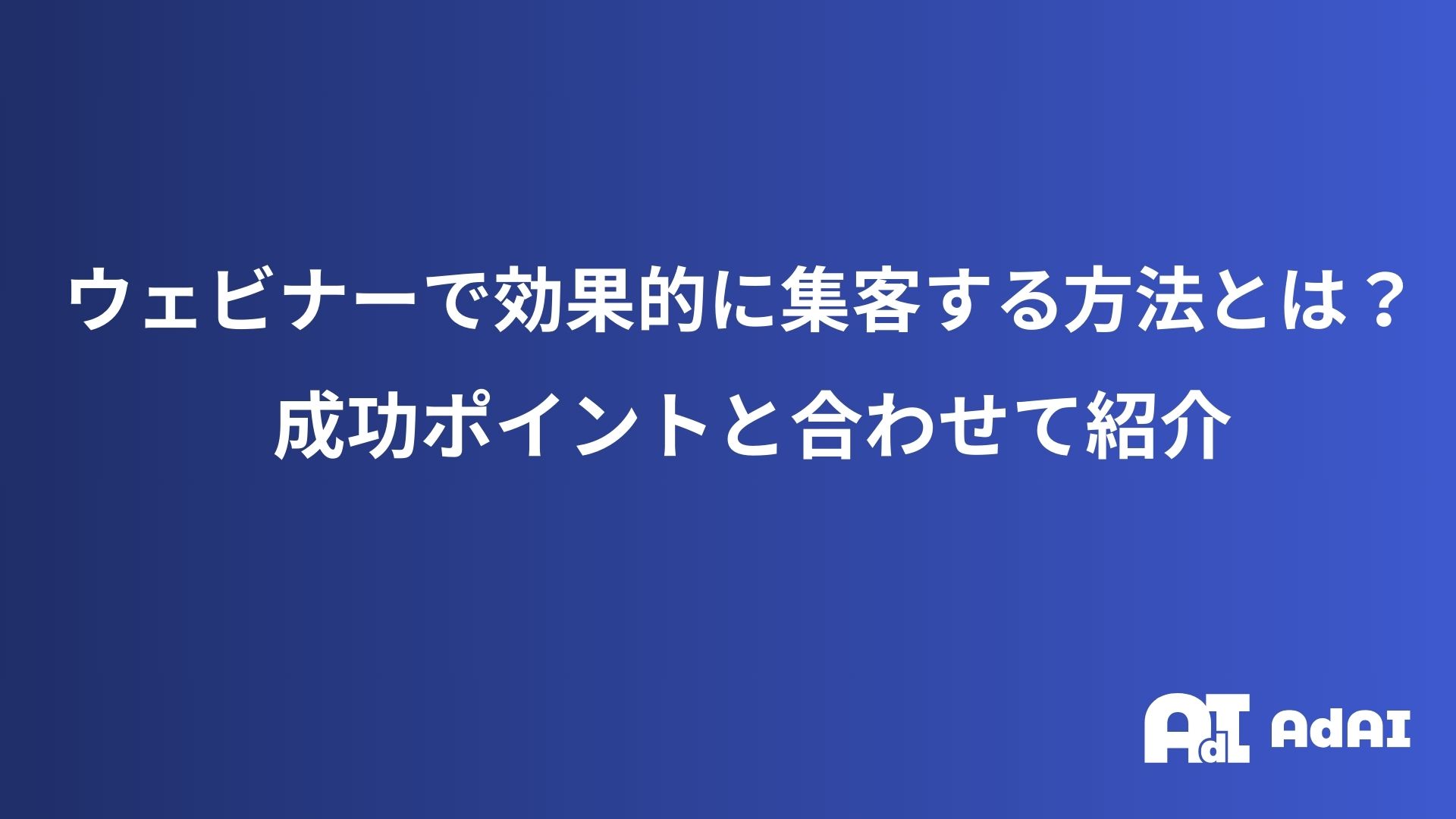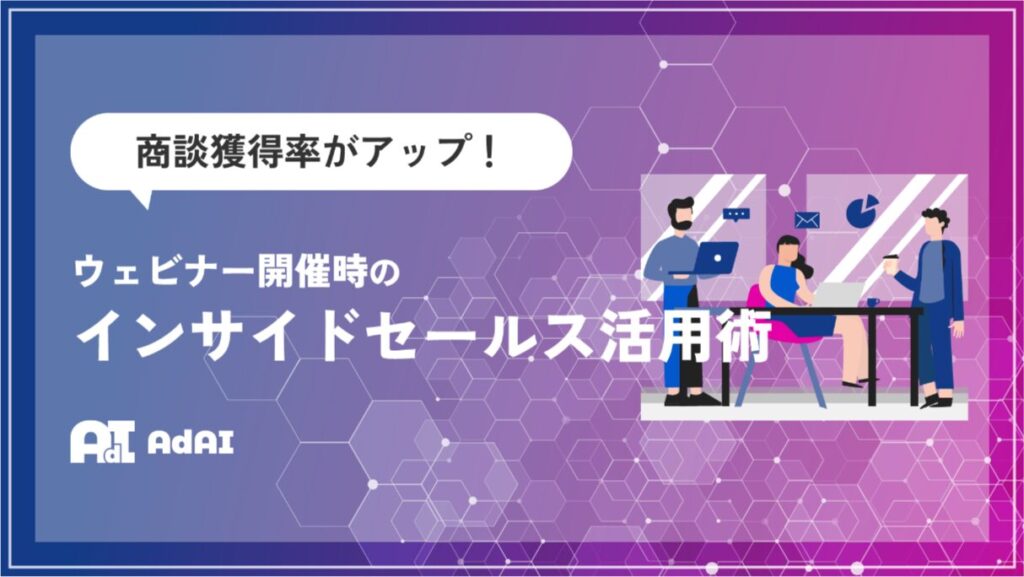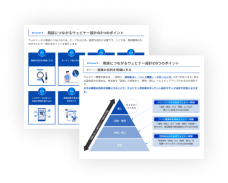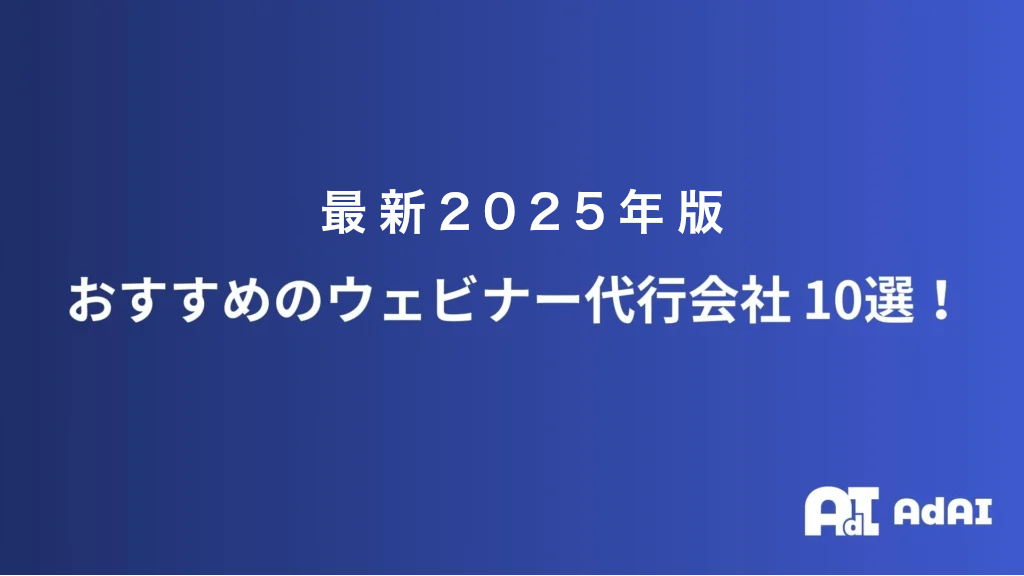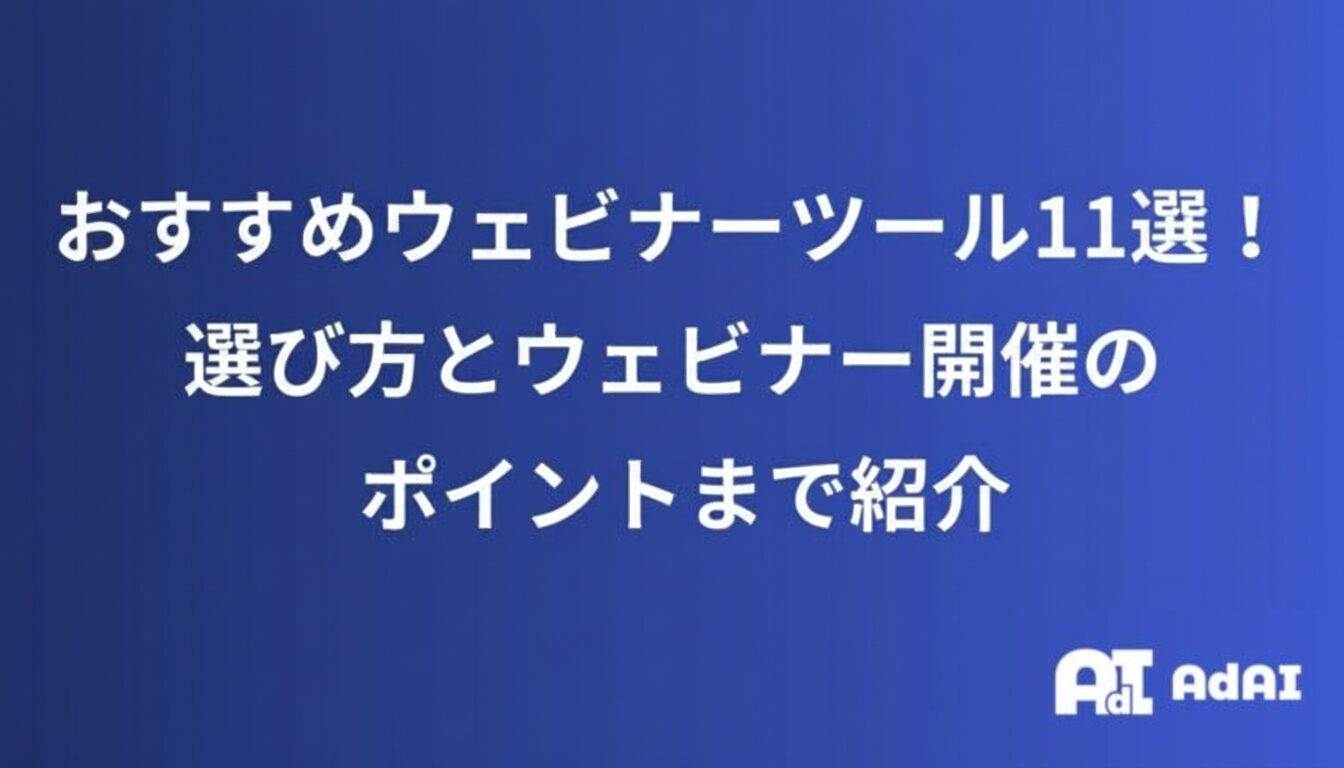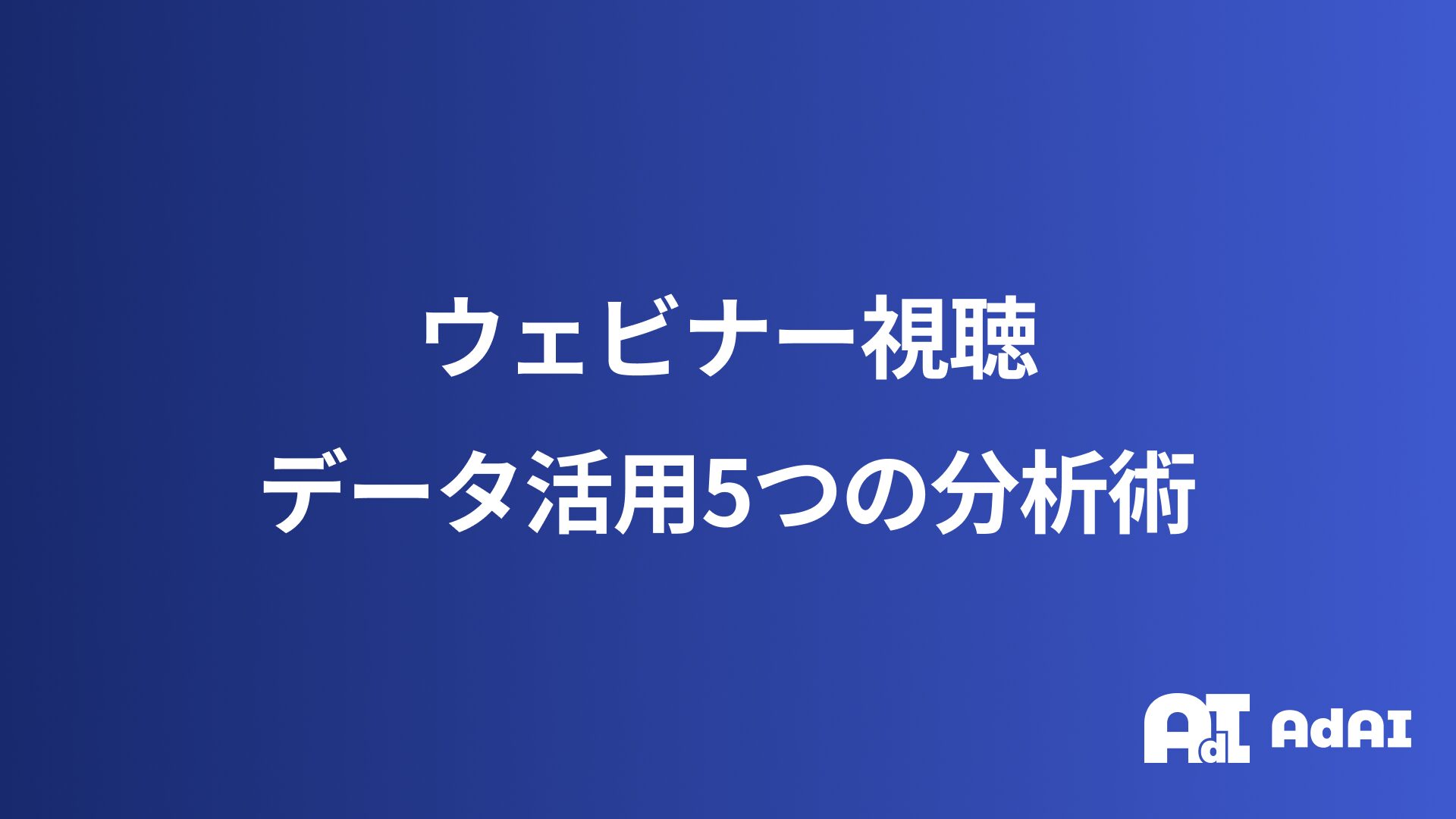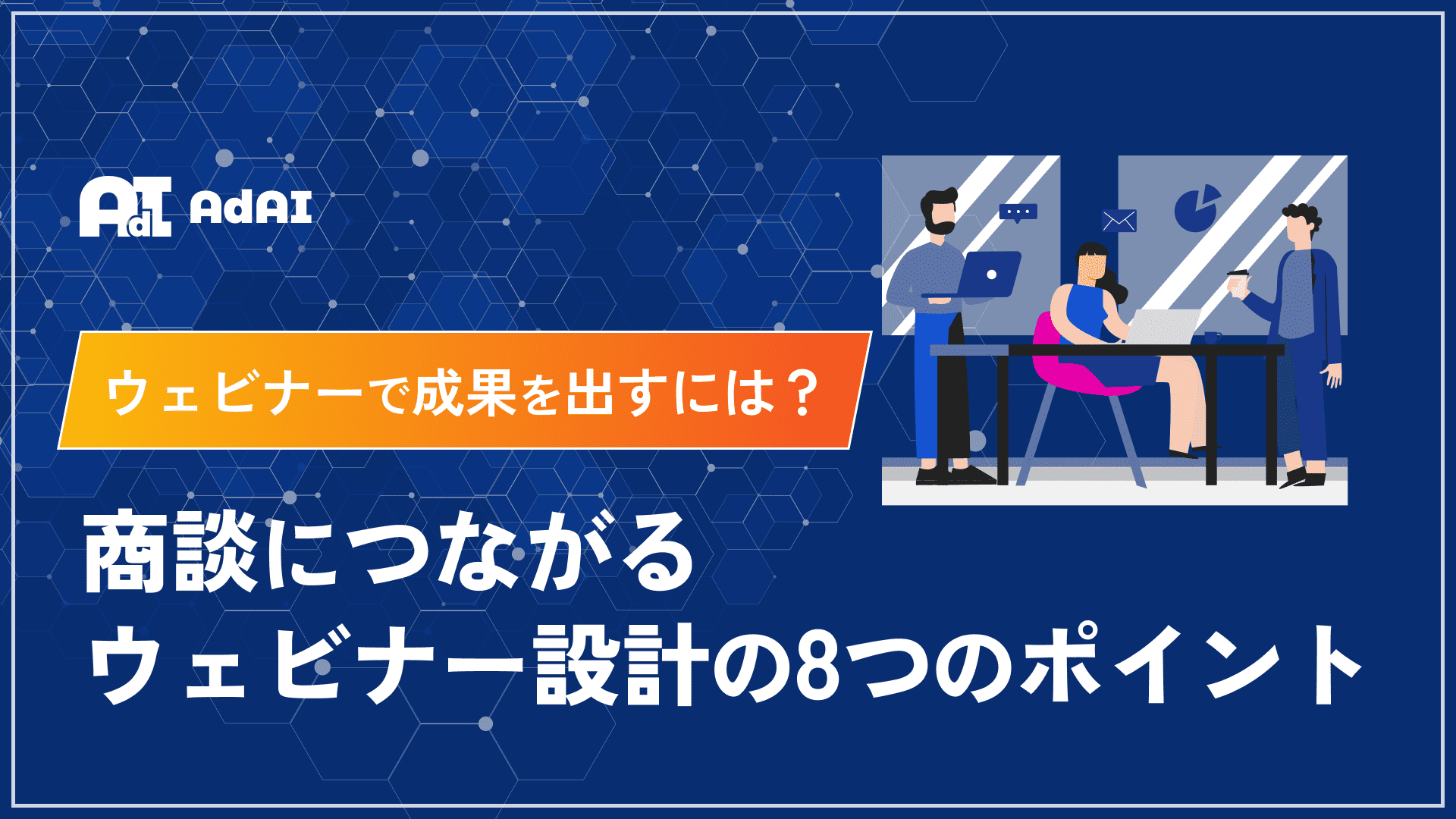「ウェビナーを開催しても参加者が集まらない」
「告知はしているのに申込率が低い」
「集客施策が正しいのか判断できない」
ウェビナーは現代のビジネスにおいて重要なマーケティング手法ですが、多くの企業が集客段階で課題を抱えています。参加者を集められなければ、どれだけ優れたコンテンツを用意しても成果にはつながりません。
本記事では、200社以上のウェビナー開催実績から導き出された効果的な集客方法と、成功させるための具体的なステップを解説します。自社での内製が難しいと感じた場合の対処法についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
\ウェビナーを商談につなげる8つのポイントとは?/
ウェビナーとは何か
ウェビナーとは、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた造語で、インターネットを通じて行われるオンラインセミナーのことです。地理的な制約を超えて参加できるため、企業のリード獲得や既存顧客への情報提供など、BtoBマーケティングの重要な手法として定着しています。
ウェビナーの主なメリットは以下の通りです:
- 全国・海外からの参加が可能:会場の制約がなく、より多くの見込み顧客にリーチできる
- コスト効率の高さ:会場費や交通費が不要で、運営コストを抑えられる
- 録画の再利用性:一度開催したコンテンツを資産として活用でき、欠席者へのフォローや営業資料としても使える
- データ分析が容易:参加者の行動データ(視聴時間、離脱ポイントなど)を取得し、次回の改善に活かせる
一方で、これらのメリットを最大化するには、適切な集客施策と運営ノウハウが不可欠です。特に初めてウェビナーを開催する企業では、告知方法の選定や参加率向上の施策設計に課題を感じるケースが多く見られます。
ウェビナーの集客方法
効果的な集客には、複数のチャネルを組み合わせた戦略的なアプローチが必要です。ここでは、実際に多くの企業が活用している4つの主要な集客手法と、それぞれの実践ポイントを解説します。
ウェブサイトでの告知
自社の信頼性を活かした集客の起点
企業のウェブサイトやブログは、ウェビナー集客の基盤となるプラットフォームです。すでに自社に関心を持っている訪問者に対して情報を届けられるため、申込率が高い傾向にあります。
効果を高めるポイント:
- 専用ランディングページの作成:ウェビナーの価値提案を明確に伝え、参加メリットを具体的に提示する
- 登録フォームの最適化:入力項目を最小限にし、スマートフォンでも申し込みやすい設計にする
- 関連コンテンツとの連携:ウェビナーテーマに関連するブログ記事やホワイトペーパーからの導線を設計する
ただし、ウェブサイトだけでは既存の訪問者にしかリーチできないため、新規見込み客の獲得には他の施策との組み合わせが不可欠です。
SNSでの告知
拡散力を活かした認知拡大施策
Facebook、Twitter(X)などのSNSは、既存フォロワーだけでなく、シェアによる二次拡散も期待できる集客チャネルです。BtoB企業でもSNSを活用することで、業界関係者や見込み客への認知を広げることができます。
効果を高めるポイント:
- 視覚的な訴求:アイキャッチとなる画像やショート動画で注目を集める
- 複数回の投稿設計:開催1ヶ月前、2週間前、3日前、当日など、タイミングを分けて告知する
- ハッシュタグ戦略:業界特有のハッシュタグやトレンドワードを活用して発見されやすくする
- エンゲージメント促進:投稿へのコメントに丁寧に返信し、参加を促す対話を設計する
SNS運用には継続的な投稿と分析が必要となるため、専任担当者がいない場合はリソース確保が課題となります。
Web広告
ターゲット層にピンポイントでリーチ
Google広告やFacebook広告などの有料広告は、ターゲット属性を絞り込んで配信できるため、短期間で効率的に見込み客を集められます。特に新規顧客の獲得を目的とする場合に有効です。
効果を高めるポイント:
- 精緻なターゲティング設定:業種、職種、役職、興味関心などで絞り込み、適切なユーザーに配信する
- 訴求メッセージの最適化:参加するメリットを明確にし、クリック率を高める文言を設計する
- リターゲティング活用:一度LPを訪問したが申し込まなかったユーザーに再アプローチする
- 費用対効果の測定:申込単価(CPA)を継続的にモニタリングし、配信設定を調整する
ただし、広告運用には専門知識が必要で、効果的な運用ができなければ広告費が無駄になるリスクがあります。特にターゲティング設定やクリエイティブ制作、運用改善のPDCAには経験とノウハウが求められます。
プレスリリース
メディア露出による信頼性向上
プレスリリースは、メディアや報道機関を通じてウェビナー情報を発信する手法です。メディアに取り上げられることで、自社の信頼性向上と幅広い認知獲得が期待できます。
効果を高めるポイント:
- ニュース性の担保:業界初の取り組みや時流に合ったテーマなど、メディアが取り上げたくなる角度を設計する
- 配信先の選定:業界専門メディアや地域メディアなど、ターゲット層が接触するメディアを選ぶ
- わかりやすい構成:5W1Hを明確にし、記者が記事化しやすい情報設計を心がける
プレスリリースは即効性は低いものの、メディア掲載されれば高い信頼性と認知拡大効果が得られます。ただし、メディアリレーションの構築には時間がかかるため、継続的な広報活動が重要です。
ウェビナー集客を成功させる5つのポイント

集客施策を実施するだけでは不十分です。申込率と参加率を最大化するには、ユーザー体験を考慮した細やかな設計が求められます。ここでは、多くの企業が見落としがちな5つの重要ポイントを解説します。
1.特典を用意する
参加ハードルを下げる具体的なインセンティブ設計
ウェビナー参加には時間を割くという心理的コストが伴います。参加者に「時間を使う価値がある」と感じてもらうため、魅力的な特典の提供が効果的です。
効果的な特典の例:
- 実務で使える資料:チェックリスト、テンプレート、業界レポートなど、すぐに業務で活用できるもの
- 限定コンテンツ:ウェビナー参加者だけが得られる追加情報や事例資料
- 個別相談の機会:参加者限定で専門家への相談枠を提供
- 割引特典:自社製品・サービスの特別割引(既存顧客向けウェビナーの場合)
ただし、特典目当ての冷やかし参加を避けるため、ウェビナーの内容と関連性の高い特典を選ぶことが重要です。また、特典の魅力度と配布タイミング(事前配布か事後配布か)の設計には、参加率とエンゲージメントのバランスを考慮した戦略が必要となります。
2.告知内容は簡潔に
3秒で価値が伝わるメッセージ設計
ユーザーは多くの情報に日々触れており、長文の告知は読まれません。簡潔で分かりやすい告知文で、ウェビナーの価値を瞬時に伝えることが重要です。
告知に必須の要素:
- 明確なベネフィット:参加することで得られる具体的な成果(「○○の方法がわかる」など)
- ターゲットの明示:誰向けのウェビナーかを明確にする(「マーケティング担当者向け」など)
- 日時と所要時間:参加者がスケジュール調整できる情報
- 登録への導線:ワンクリックで申し込めるCTAボタン
- 講師の権威性:信頼性を示す実績や肩書き
視覚的な訴求も重要です。キャッチーなアイキャッチ画像や、参加メリットを端的に示すキャッチコピーを活用することで、スクロール中のユーザーの目を引くことができます。
3.応募方法を整える
離脱を防ぐ申込フォームの最適化
申し込みフォームでの離脱は、集客施策の効果を大きく損ないます。ユーザーがストレスなく登録できる設計が、申込率向上の鍵となります。
最適化のポイント:
- 入力項目の最小化:必須項目は氏名、メールアドレス、会社名程度に留める(営業活用したい情報は後日アンケートで取得)
- レスポンシブデザイン:スマートフォンでも入力しやすいフォームサイズとボタン配置
- エラー表示の親切設計:入力ミスを即座に分かりやすく表示する
- 登録完了の明示:「登録完了」と「次のステップ」を明確に伝える
- セキュリティの明示:個人情報の取り扱いポリシーを明記し、安心感を与える
フォームの最適化は技術的な知見が必要で、ABテストを通じた継続的な改善が求められます。特にBtoB企業では、企業ドメインのメールアドレス入力を促す工夫など、リード品質を保ちながら申込率を高める設計が重要です。
4.リマインドメールは必須
申込者の参加率を高める継続的なコミュニケーション
ウェビナー申込者の実際の参加率は一般的に50〜60%程度と言われています。申し込みから開催日までの期間が空くと、参加者が忘れてしまうためです。リマインドメールの送信は、参加率を大きく左右する重要施策です。
効果的なリマインド設計:
- 3回のリマインド配信:1週間前、前日、当日朝の計3回が基本
- アクセス情報の明記:URL、ID、パスワードなど、参加に必要な情報を毎回記載
- 参加メリットの再訴求:「こんなことが学べます」と価値を再確認させる
- モバイル最適化:スマートフォンからでも見やすく、クリックしやすいメール設計
- カレンダー登録機能:.icsファイルを添付し、予定登録を促す
リマインドメールの文面、配信タイミング、件名の工夫など、細部の最適化が参加率に直結します。特に開催当日朝のリマインドは、「今日だったことを忘れていた」という離脱を防ぐ最後の砦となります。
5.アンケートとフィードバックで今後のウェビナーに活用する
データに基づく継続的な改善サイクルの構築
ウェビナーを単発で終わらせず、次回以降の質を高めるには、参加者からのフィードバック収集と分析が不可欠です。
アンケートで取得すべき情報:
- 満足度評価:内容、講師、時間配分、資料などの各要素別の評価
- 参加目的と達成度:期待していた情報が得られたか
- 次回への要望:聞きたいテーマや形式の希望
- 商談意欲:製品・サービスへの興味度合い(ホットリードの発掘)
- 改善ポイント:不満や分かりにくかった点の自由記述
収集したデータは、次回のウェビナー企画に活かすだけでなく、営業部門へのリード引き継ぎにも活用できます。ただし、アンケート結果の分析と改善アクションへの落とし込みには、データ分析スキルとマーケティング知見が必要です。
多くの企業では、アンケートは実施するものの、結果を十分に活用できていないケースが見られます。PDCAサイクルを効果的に回すには、データドリブンな改善プロセスの設計が重要となります。
\商談率を上げるインサイドセールス活用術とは/
ウェビナーを成功させる3つのステップ

ウェビナーの成功には、企画から開催、フォローアップまでの一連の流れを戦略的に設計することが重要です。ここでは、実践的な3つのステップと各段階で押さえるべきポイントを解説します。
ステップ1.企画段階
目的とターゲットを明確にした戦略設計
ウェビナーの成否は企画段階で大きく左右されます。まず明確にすべきは「誰に、何を、なぜ届けるのか」です。
企画で定義すべき要素:
ウェビナーの目的設定
- 新規リード獲得:製品・サービスの認知拡大と見込み客の情報取得
- 商談創出:具体的な課題を持つ見込み客に解決策を提示し、商談につなげる
- 既存顧客のエンゲージメント強化:活用事例やアップデート情報の共有
ターゲット設定の具体化
- ペルソナの明確化:業種、職種、役職、抱えている課題
- 参加動機の想定:どんな情報を求めているか、どんな悩みを解決したいか
- 接触チャネルの特定:ターゲットがよく利用する情報源やSNS
コンテンツ設計
- 参加者が得られる具体的な学びや解決策
- ウェビナーの時間配分(講演・デモ・質疑応答の割合)
- 講師の選定(専門性と訴求力のバランス)
- 差別化ポイント(競合ウェビナーとの違い)
企画段階では、市場調査、競合分析、過去データの分析など、多角的な視点が求められます。特に初めてウェビナーを開催する企業では、どのようなテーマが響くか、どの程度の規模を目指すべきかの判断が難しく、経験に基づく知見が重要になります。
ステップ2.集客の準備
効果的な告知とプロモーション戦略の実行
企画が固まったら、ターゲットに確実に届く集客施策を展開します。複数のチャネルを組み合わせた統合的なアプローチが効果的です。
告知コンテンツの作成
- ランディングページ:ウェビナーの価値を明確に伝える専用ページ
- 告知用クリエイティブ:SNS投稿用の画像・動画、バナー広告素材
- メール文面:開封率を高める件名と、申込を促す本文設計
- プレスリリース:メディア向けの訴求ポイントをまとめた資料
チャネル別の施策展開
- 自社チャネル:ウェブサイト、ブログ、既存顧客リストへのメール配信
- SNS:Facebook、Twitter(X)での複数回投稿とハッシュタグ戦略
- 有料広告:Google広告、SNS広告でのターゲティング配信
- パートナー連携:関連企業や業界団体を通じた告知
集客スケジュールの設計
- 開催4週間前:告知開始、ランディングページ公開
- 開催2週間前:SNS投稿強化、リマインドメール第1弾
- 開催1週間前:広告配信開始、プレスリリース配信
- 開催3日前:最終告知、申込締切の案内
集客準備では、各チャネルの特性を理解した上での最適な配信設計が必要です。特に有料広告の運用では、ターゲティング精度やクリエイティブの質が費用対効果に直結するため、専門的な運用スキルが求められます。また、申込状況をリアルタイムでモニタリングし、必要に応じて施策を調整する柔軟な対応も重要です。
ステップ3.プロモーションの準備
参加体験の最大化と商談化への導線設計
ウェビナーは開催して終わりではありません。当日の運営品質と事後フォローが、最終的な成果を左右します。
当日の運営ポイント
- 開始前の準備:接続テスト、資料の最終確認、バックアップ体制の構築
- スムーズな進行:時間管理、わかりやすい説明、参加者の集中力維持
- 質疑応答の設計:事前質問の収集、リアルタイム質問への対応、回答できない質問の記録
- トラブル対応:音声・映像トラブルへの即座の対処
事後フォローの実施
- 即日対応:参加者へのお礼メール送信(録画URLや資料の共有)
- アンケート収集:満足度調査と次回への要望ヒアリング
- ホットリードの抽出:アンケート結果や視聴行動から商談意欲の高い見込み客を特定
- 営業部門への連携:リード情報と参加状況を営業チームに引き継ぐ
- 欠席者フォロー:申込したが参加できなかった方への録画案内
継続的な改善
- 参加者データの分析(申込率、参加率、視聴時間、離脱ポイント)
- アンケート結果の定量・定性分析
- 次回ウェビナーへの改善アクションの策定
当日運営では、技術的なトラブル対応力と臨機応変な進行管理が求められます。また、事後フォローでは、データ分析に基づく効果測定と、商談化への適切な導線設計が必要です。これらのプロセスを社内で完結させるには、複数部門の連携と専門スキルを持つ人材が不可欠となります。
自力でのウェビナー開催が難しいと感じたら外注も検討
ここまで解説してきたように、ウェビナーを成功させるには企画から集客、運営、事後フォローまで、多岐にわたる専門的なノウハウが必要です。実際に多くの企業が、以下のような課題に直面しています。
内製で直面する主な課題
リソース不足
- マーケティング担当者の日常業務に加えてウェビナー運営を行う時間的余裕がない
- 企画、集客、運営、分析と各フェーズで複数の担当者が必要だが人員が足りない
- 他の施策との優先順位調整が難しく、ウェビナーに十分なリソースを割けない
専門スキルの不足
- Web広告の効果的な運用経験がなく、広告費が無駄になるリスクがある
- ランディングページの制作やフォーム最適化のノウハウがない
- データ分析と改善施策の立案に必要なマーケティング知見が不足している
- 当日の技術トラブル対応や配信品質の確保に不安がある
ノウハウの蓄積が困難
- 年に数回しか開催しないため、ナレッジが組織に蓄積されない
- 担当者の異動や退職でノウハウが失われてしまう
- 何が正解か分からず、試行錯誤に時間とコストがかかる
こうした課題を抱える企業にとって、ウェビナー開催に精通した専門企業への代行は有効な選択肢となります。
AdAIのウェビナー支援サービス
AdAIは200社以上のウェビナー開催を支援してきた実績があり、企画から商談獲得までを一気通貫でサポートします。
ウェビナーの企画立案から当日運営、事後フォローまで、成果に直結する全プロセスを支援するプランです。
商談化への導線構築:リードスコアリングと営業部門への適切な引き継ぎ
戦略的な企画設計:ターゲット分析に基づくテーマ設定とコンテンツ企画
効果的な集客施策:Web広告運用、LP制作、SNS運用などの統合的な集客支援
安定した運営サポート:当日の技術サポートと進行管理
まとめ:ポイントを押さえてウェビナー集客を成功させよう
ウェビナーは、BtoBマーケティングにおいて効果的なリード獲得手法ですが、成功には戦略的な企画、効果的な集客施策、そして丁寧な運営と事後フォローが不可欠です。
本記事で紹介した集客方法と成功ポイントを実践することで、申込率と参加率を高め、商談につながるウェビナーを実現できます。自社での開催に課題を感じる場合は、専門企業への代行も選択肢として検討してみてください。
ウェビナーを通じて、より多くの見込み客との接点を創出し、ビジネス成果の向上を目指しましょう。